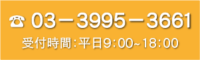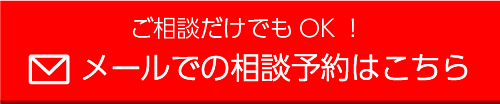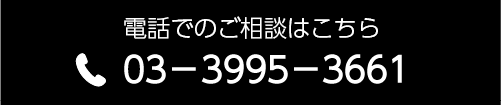お客様から「これは社員に対する福利厚生費として認められますか?」という質問をいただくことがよくあります。
昨今の働き方改革に伴い、福利厚生の充実は社員の労働意欲の向上・離職防止に効果的だと言えます。
しかし、福利厚生費を経費計上するためには、一定の要件を満たす必要があります。要件を満たしていない場合は経費として認められないだけではなく、社員に対する給与とみなされてしまうこともあります。
そこで今回は、福利厚生費として経費計上するための要件や具体例を解説します。
1.福利厚生費とは
福利厚生費とは、社員が快適に働き、生活を安定させるために会社が負担する費用で、給与や賞与とは区別されます。
福利厚生費は大きく分けて2種類存在します。
・法定福利厚生費
法律により企業に負担する義務が課されているものです。
社員が加入要件を満たす場合は加入が必須であり、各種保険に割り当てられた料率分を企業が負担する必要があります。
例)健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料等
・法定外福利厚生費
企業が任意で行うもので、社員の満足度や働きやすさを高める目的で導入されます。
内容や支給額は自由に設計できます。
例)住宅手当、昼食補助、社員旅行費用、研修費用等
法定福利厚生費は法律で定められているものですので、当然会社の経費として認められます。また、社員の経済的利益としては扱われないことから、課税されることもありません。
一方、法定外福利厚生費はその名のとおり法律上に明確な規定がなく、取り扱いを誤ると給与とみなされ、社員に所得税、住民税、社会保険料等の負担が追加で課される場合もあります。
ここからは、この法定外福利厚生費について解説します。
2.福利厚生費として認められるための条件
福利厚生費として認められるためには3つの要件があります。
1)全社員を対象としていること
すべての社員が公平に利用できるものであることが、福利厚生費として認められるための要件となります。
例えば、役職や部署によって利用できる福利厚生に差がある場合、機会の平等が保たれていないため、福利厚生を利用できる社員に対する現物支給として扱われ、給与課税されます。
2)現金や換金性の高いものでないこと
福利厚生はモノやサービスの提供であることが前提です。
そのため、現金や金券等の換金性の高いものを支給した場合、給与として扱われ給与課税対象になります※。
※社員への食事補助等、一部福利厚生費として認められるものもあります。
こちらについては後述いたします。
3)社会通念上妥当な金額であること
金額が社会通念上妥当であるかも、重要な判断要素になります。
なかには明確な金額の上限が定められていない場合もあります。そのような場合は、同規模の会社や同業界の平均と比較して、高額過ぎないか総合的に判断することになります。
3.福利厚生費の具体例
【2.福利厚生費として認められるための条件】で説明した要件を満たすことで、次のような費用が福利厚生費として認められる場合があります。
その中でもお問い合わせの多いものをいくつか紹介させていただきます。
1)社員旅行
社内の親睦と社員の勤労意欲向上を目的として行われるものであって、次のいずれも満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を福利厚生費とすることができます。
①旅行の期間が4泊5日以内であること
②旅行に参加した人数が全体の人数の50パーセント以上であること
なお、金額については明記がありませんが、国税庁のホームページ上の事例では、一人当たりの会社負担額が10万円の場合は給与課税されないと判断されています。そのため、一人当たりの旅費が10万円以下であれば社会通念上妥当な金額と判断するのが一般的です。
また、自己都合で旅行に参加しなかった人に金銭を支給する場合には、参加者と不参加者の全員にその不参加者に対して支給する金銭の額に相当する額の給与の支給があったものとされます。
(参照:国税庁「タックスアンサーNo.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行」)
2)食事補助
役員や使用人に支給する食事は、次の2つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。
①役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること
②次の金額が1か月当たり3,500円(税抜)以下であること。
(食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)
例えば1か月当たりの食事の価額が5,000円で、社員の負担している金額が2,500円の場合、その負担額を控除した残額(2,500円)が福利厚生費として認められます。
一方で、社員の負担額が2,000円の場合だと①を満たしませんので、負担額を控除した残額(3,000円)が給与課税されます。
なお、残業または宿日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しなくてもよいことになっています。
(参照:国税庁「タックスアンサーNo.2594 食事を支給したとき」)
3)健康診断・人間ドック
1年に1回受ける健康診断については、福利厚生費として計上することができます。
人間ドックについても、希望者全員(年齢等による制限は可)に受けさせている場合は、福利厚生費として認められます。
(参照:国税庁「質疑応答事例 人間ドックの費用負担」)
4)社宅
社宅は、条件を満たすことで福利厚生費として扱われます。
①会社が所有している、または会社名義で借りている物件であること
②賃借料相当額の50%を社員から徴収していること
賃借料相当額は次のⅰ~ⅲの計算式で算出した金額の合計になります。
ⅰ.(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2パーセント
ⅱ.12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
ⅲ.(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22パーセント
(参照:国税庁「タックスアンサーNo.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき」)
なお、現金支給による住宅手当は給与扱いになります。
5)資格取得・研修費
業務に直接関係のある資格の取得費用や研修費等であって、その費用が高額すぎないものであれば福利厚生費になります。
なお、資格取得時に支給する祝い金や報奨金は給与課税となります。
(参照:国税庁「タックスアンサーNo.2601 職務に必要な技術などを習得する費用を支出したとき」)
6)制服の支給
制服については、次のような場合ですと福利厚生費として扱われます。
①専ら勤務する場所において通常の職務を行う上で着用するものであること
②私用には着用しないまたは着用できないものであること
③支給又は貸与が全員を対象としていること
そのため、例えばスーツのような、私用に着用できるものを制服として支給する場合は、給与課税されます。
(参照:国税庁「質疑応答事例 背広の支給による経済的利益」)
4.会議費・接待交際費との違い
福利厚生費は他の経費と性質が似ており、判断に迷う場合があります。
例えば、同じ飲食費でも内容によって次のように異なってきます。
・社内会議中の弁当代 ⇒ 会議費※1
・取引先との食事代(1人当たり1万円以下) ⇒ 会議費
・社員の休憩用の飲物代 ⇒ 福利厚生費※2
・社員全員を対象とした慰労会費用 ⇒ 福利厚生費
・取引先を招いての懇親会費用 ⇒ 接待交際費
・特定の社員のみを対象とした懇親会費用 ⇒ 接待交際費
※1 「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」であれば、認められるとされています。
※2 社員の誰もが食べることができる場合に限ります。例えば、一部の社員のみしか食べることができない場合は、給与扱いになる可能性があります。
誰(社員の全員または一部のみか、それとも社外の者とか)と、何の目的(打合せ、接待、社員の慰労等)で支出したのかを明確にし、経費の分類間違いをしないよう注意してください。
5.まとめ
今回は法定外の福利厚生費について解説させていただきました。
福利厚生費をうまく活用することで、社員の満足度向上とあわせて会社の節税対策を進めることもできますが、経費として認められるためには「全社員を対象」「現物やサービスの提供であること」「金額の妥当性」といった要件を満たす必要があります。
また、会議費や接待交際費等、福利厚生費と混同しやすい勘定科目もあります。
区別を間違えないよう、領収書の保管や、飲食費であれば「誰と食事をしたのか」等も忘れず記録しておきましょう。
その他、本記事で触れた内容に関連したコラムもいくつか公開しています。
よろしければそちらもご覧くださいませ。
福利厚生の要件は複雑です。自社だけで判断するのが難しいときは、どうぞ弊所までお問い合わせください。